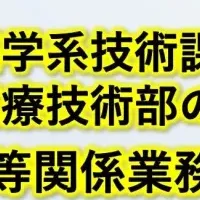

兵庫発!自動運転トラックの合流を円滑にする新システム登場
兵庫発!自動運転トラックの合流を円滑にする新システム登場
神戸市に本社を構える三菱重工業株式会社とそのグループ会社、三菱重工機械システム株式会社(MHI-MS)が新たに開発した合流支援情報提供システムが、いよいよ本格的な実証実験を迎えます。このシステムは、自動運転トラックが高速道路に安全に合流できるよう、車両の走行情報をセンサーを介して提供し、運転を支援する重要な役割を果たします。
実証実験の概要
このシステムが関与する実証実験は、国土交通省とNEXCO中日本が共同で実施し、2023年3月3日から新東名高速道路の一部区間で行われます。具体的には、駿河湾沼津SAから浜松SAまでの区間であり、この試みは国内初となる自動運転トラックの公開実検証となります。深夜帯に設定された自動運転車優先レーンでは、合流支援情報提供システムがその効力を発揮します。
合流支援情報提供システムの機能
MHI-MSが開発したこのシステムでは、あらかじめ設置されたセンサーが本線道路を走行する車両の情報をリアルタイムで取得し、路側処理装置を介して合流を試みるトラックに伝達します。この情報は、トラックが加速車線に入るずっと前から把握できるため、ドライバーは安全に合流のタイミングを見極めることが可能になります。結果として、トラックは本線の流れを把握し、余裕を持って速度を調整できます。
安全性と利便性の向上
合流支援情報提供システムにより、トラックが本線に合流する際の安全確保が大幅に改善される見込みです。加速車線に入る前から本線の状況がわかるため、トラックは常に安全な速度で運行でき、他の車両に影響を与えるリスクが軽減されます。このような先進的な情報提供は、従来の運転方法では実現が難しかったものです。
多様な情報サービスの充実
このシステムは、ETC2.0などの高度な情報サービスとの連携も可能であり、自動車同士が直接通信する「ITS Connect」を通じて、運転支援に必要な周辺情報も得られます。このため、自動運転トラックだけでなく、一般の非自動運転車両にも利益をもたらすと期待されています。
デジタルライフライン計画に沿った取り組み
国土交通省は「デジタルライフライン全国総合整備計画」を推進しており、本実証実験はその一環として具体的な施策です。このような取り組みを通じて、自動運転技術の安全性と効率性を高めるための環境整備が図られています。三菱重工グループは、長年にわたり培われた料金収受システムやセンシング技術を自動運転支援の基盤として活用し、安全で便利な次世代の交通インフラを築くことを目指しています。
今後の展望
この合流支援情報提供システムは、今後の自動運転技術の進展に重要な役割を果たすことでしょう。そして、2024年には新東名高速道路の未供用区間で行われる「路車協調実証実験」にも参加し、さらなる進化を促進する予定です。
私たちの道路交通がどのように変わるのか、次世代モビリティの進化を今後も見守り続けたいと思います。

トピックス(その他)
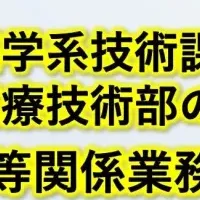
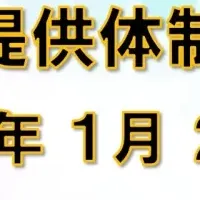
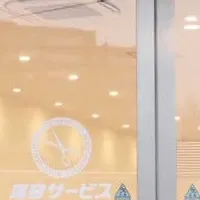
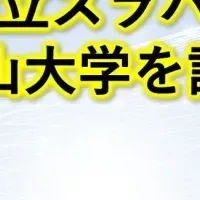
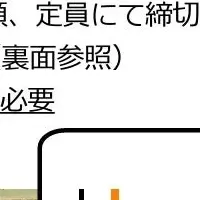
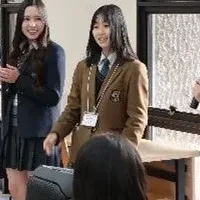

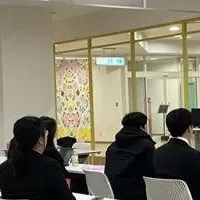


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。