

高校生が取り組む海洋プラスチック問題:つながる未来への一歩
高校生が取り組む海洋プラスチック問題:つながる未来への一歩
2025年7月26日(土)、兵庫県西宮市の古野電気株式会社において、阪神間の高校生たちが海洋プラスチック問題に取り組む特別なイベントが開催されました。この取り組みは、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)支援事業の一環として実施され、学生たちが未来の課題に目を向ける貴重な機会となりました。
当日は、大阪府と大阪大学の協力を得て、5校から計33名の高校生と教員が参加しました。生徒たちは、まず大阪湾の海洋ごみ流出の現状について説明を受け、その後、最新のAIを活用した海洋流出の研究結果も紹介されました。このような実体験から、学生たちは社会課題の重要性を実感することができたでしょう。
地元企業の積極的な姿勢
古野電気は、海に育てられた企業として、海洋プラスチック問題を自社の社会的責任と捉えています。今年の2月には大阪府と大阪大学との連携協定を結び、海に流出するゴミの解決に向けた取り組みを加速させています。このイベントは、次世代を担う生徒たちが最新の課題解決の手法を学ぶことを目的としています。
実体験を通じた学び
参加した高校生たちは、古野電気の大型水槽実験施設を使用して、魚群探知機を用いた海洋プラスチックごみの探知評価実験を行いました。さらに、グループに分かれて、各自が設定したテーマについて意見を交換し、課題を発表しました。
生徒たちは、海洋生分解性プラスチックや個々の意識改革の重要性について、多角的な視点から発表し、真剣に考える機会を得ました。また、イベント後のアンケートでは、「問題へのアプローチが多様であることが分かり、広い視点を持つ重要性を感じた」や「一歩ずつ行動を起こすことが大切だと思う」といった声が寄せられました。
次世代の意識を育む
今回のイベントを通じて、生徒たちは社会課題に対する探究心を深め、未来に向けて向かう姿勢を育むことができたようです。古野電気では、今後も地域との連携を大切にしながら、環境問題解決に向けた取り組みを続けていく予定です。
海の未来をつなげるために、古野電気は「好きになってもらうこと」から始めるという理念を大切にしています。身近な海の魅力を知ることで、生徒たちが自然を大切に思う気持ちを育て、社会全体が海を守る行動に繋がることを期待しているのです。
まとめ
今回の取り組みは、まさに未来を担う高校生たちの意識を育成する試みでした。海洋プラスチック問題は我々全員が関与すべき重要なテーマであり、このような活動を通じて、未来を見据える選択が育まれることを願っています。







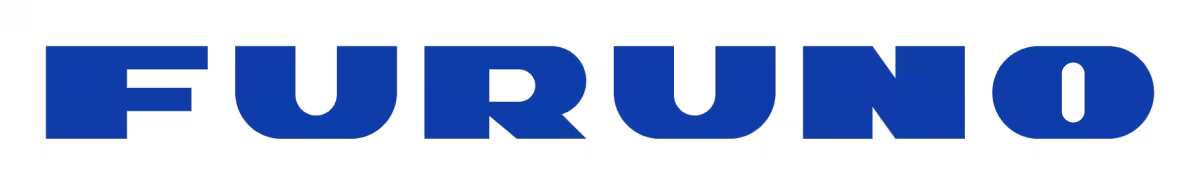
トピックス(その他)





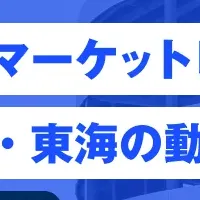
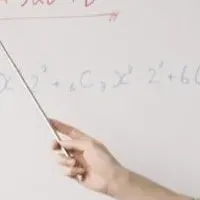
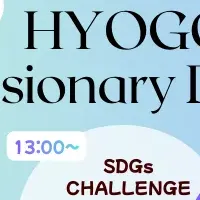


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。