

尾道造船と常石造船が革新的な貨物船Bingo42を共同開発
尾道造船と常石造船の共同開発により生まれた「Bingo42」
最近、尾道造船株式会社と常石造船株式会社がタッグを組み、42,200トン型のばら積み貨物船「Bingo42」を共同で開発しました。このプロジェクトの背景には、両社が船舶の開発にかかる設計負荷の増大を懸念し、それに対応するための効率的な開発体制構築がありました。
一般的に、日本の造船所は個別に基本設計から生産設計に至るまでのプロセスを行うため、船舶の新たな設計には膨大な時間とコストがかかります。しかし、今後は代替燃料船の必要性が高まり、設計作業の負担がさらなる増加が予想されます。このような時代背景の中で、両社は地理的な近接性を生かし、共通の問題意識を持って協力を開始しました。
共同開発の狙いと進捗
共同開発では、お互いの設計・建造に関する技術や考え方を共有し、従来船型からの価値向上について話し合いを重ねました。その結果、船型の全長を3メートル延長し、設計の最適化を実現しました。これにより、尾道造船の40BCモデルからは積載能力と燃費が向上、一方で常石造船のTESS42モデルからも燃費性能が改善されました。
また、新たに導入された省エネ技術「MT-FAST」により、推進性能の改善が図られ、燃費性能にも大きなプラスをもたらしています。この技術はプロペラ前方に取り付けたフィンを利用し、エネルギーの損失を低減させ、約4%の燃料削減を実現。環境規制であるEEDI基準に関しては、リファレンスラインよりも35%以上の削減を達成しました。さらに、将来的にはメタノール二元燃料化も視野に入れた設計思考がなされています。
「Bingo42」という名前の由来
開発された新型船舶は、両社が備後地方にある造船所で手がけることから、また共同による革新性と持続可能な海洋環境の貢献から「Bingo42」と名付けられました。この名は、共同開発の頭文字をつなげたもので、両社が力を合わせて建造する意図が込められています。
構造設計や建造、営業はそれぞれの企業が行いながら、コンセプト設計は統一して進めることで、シェアの拡大も狙っています。カーボンニュートラルへの対応が喫緊の課題となっている中、業界全体の未来に向けた取り組みとして、代替燃料船の研究開発の効率化が今後一層求められるでしょう。
未来に向けた期待の声
尾道造船の本屋勝幸氏は、「常石と船型開発のニーズが合致し、Bingo42を共同開発できたことを大変嬉しく思う。ハンディサイズの旗手として業界を牽引できるものになると確信している」とコメントしています。
一方、常石造船の西嶋孝典氏は、「Bingo42の開発は私たちにとって大きな喜びである。燃費性能や積載能力の向上に加え、省エネ技術を導入したことでEEDI基準を35%以上削減できた」と、その成果に自信を見せています。
総じて、Bingo42は、革新的な船舶を通じて競争力のあるソリューションを提供し、業界全体の持続可能な未来の実現に寄与していくことが期待されています。


トピックス(その他)

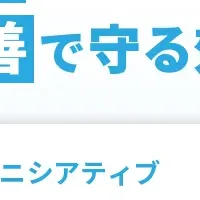

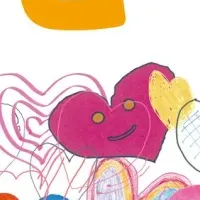
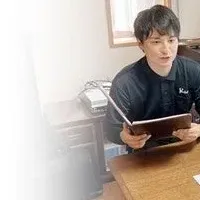




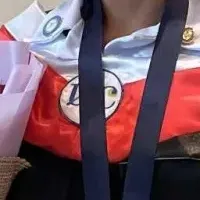
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。