

未来を見据えた子どもたちの挑戦 「お寿司で学ぶSDGs」が実施されます
未来を見据えた子どもたちの挑戦
2025年11月13日、島根県の宍道小学校で「お寿司で学ぶSDGs」という出張授業が開催されます。このイベントは、くら寿司株式会社と一般社団法人海と日本プロジェクトinしまねが共同で実施し、次世代の担い手である子どもたちに、海洋環境や食品ロス、さらには低利用魚の活用について学んでもらうことを目的としています。
実施の背景
近年、私たちの生活は漁業資源の減少や、海の生態系に関するさまざまな問題に影響されています。授業の中では、地域の漁業の現状や海の恵みの重要性を伝えるとともに、環境保護の意識を育むためのプログラムが行われます。この出張授業は、海と日本プロジェクトが目指す「美しく豊かな海を次世代に引き継ぐ」というテーマに即し、初めて島根県での開催となります。
授業では、海と日本プロジェクトinしまねが今年夏に実施した体験学習「隠岐めしと歴史探険隊」の内容も紹介し、参加児童には海洋学習の一端を感じてもらいます。そこで、具体的にどのような内容が展開されるのかを見ていきましょう。
授業内容の詳細
授業は3つのセクションに分かれており、参加する子どもたちが興味を持ちながら学びを深められるよう設計されています。
1. 海の現状を理解する
まずは、「未来ではお寿司が食べられなくなる!?」というテーマで、映像や魚模型を使って、日本の漁業が抱える問題を紹介します。資源の減少や担い手不足、さらには気候変動が漁業にどのような影響を及ぼしているかを、子どもたちが自分の問題として考えられるように伝えます。
2. お寿司屋さん体験
次に、くら寿司のオリジナル教材を使った「お寿司屋さん体験ゲーム」が行われます。この体験を通じて、過剰提供や廃棄がどのような問題を引き起こすのかを実体験で学ぶことで、食品ロスの重要性を理解します。自らの手で体験することで、より深い理解が得られます。
3. 課題解決に挑戦
最後に、児童たちがグループで意見を出し合い、「どうすればお寿司を未来にも楽しむことができるのか」をテーマに解決策を考えます。ICTの活用や低利用魚の活用について発表を行いながら、持続可能な社会に向けた学びを深めます。
特別な交流の場
この授業を通じて、海と日本プロジェクトの活動やくら寿司の取り組みがどのように海の環境を守るために連携しているのかを学ぶことができる貴重なチャンスです。島根県内の他の小学校でも同様の授業が予定されており、地域全体で子どもたちの環境意識を高める取り組みが進行しています。
取材のご案内
授業の取材も可能で、特に「低利用魚の活用」や「さかな100%プロジェクト」に関連した商品が紹介される店舗での取材が設定されています。ぜひこの機会に、未来を担う子どもたちの学びの場に訪れてみてはいかがでしょうか。
イベントに参加しよう
「お寿司で学ぶSDGs」の開催日は2025年11月13日、宍道小学校の体育館で行われます。海に関する知識を深めたい方、地元の児童の成長を見守りたい方は、ぜひ参加してみてください。
このイベントは、島根の未来を見据えた大切なステップとなるでしょう。



関連リンク
サードペディア百科事典: SDGs くら寿司 海と日本プロジェクト
トピックス(イベント)

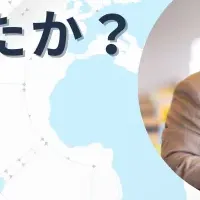



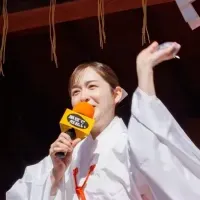
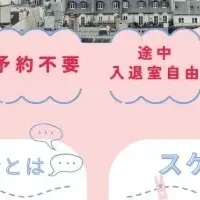
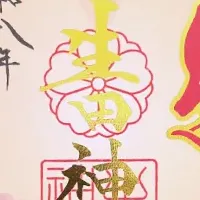


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。