

リガクが円山応挙の襖絵を科学で解明するプロジェクト
リガクが円山応挙の襖絵を科学で解明するプロジェクト
東京都に本社を構える株式会社リガクが、西日本の大乗寺で所蔵される円山応挙の貴重な襖絵について、先進的なX線分析技術を活用した測定を実施しました。この取り組みは、円山応挙の障壁画の背景金箔の色調を復元するための研究であり、文化財の保全と科学の融合を目指しています。
研究の背景と目的
円山応挙は、日本画の巨匠として名高い人物であり、彼の作品はその美しさと深い意図により、今なお多くの人々を魅了しています。しかし、その制作過程や使用された材料には未解明な部分が多く、これを明らかにするためには新しいアプローチが求められています。このたびの研究は、大乗寺の副住職である山岨眞應氏が主導し、元海上技術安全研究所の千田哲也氏や画家である東北芸術工科大学の田中武氏と共に進めているもので、X線分析を駆使して科学的に作品の真実に迫ることを目的としています。
使用される分析装置
本研究で使用されるのは、「Thermo Scientific™ Niton™ XL5 Plusハンドヘルド蛍光X線(XRF)分析計」です。これは、非破壊で素材の組成を分析できる先進的な装置です。これにより、作品を傷つけることなく、金箔の組成や使用状況を詳しく調査することが可能となります。
具体的な研究内容
1. 制作時期の検証
襖絵に使用されている金箔の組成に違いがあるかどうかを測定し、異なる時期に制作された可能性を確認することを目指しています。赤色や青色の金箔の違いが、作品の時代背景や技術的進歩を示す重要な手がかりになると期待されています。
2. 遠近表現における金箔の活用
金箔が色調にどのように影響を与えているのかも重要な分析ポイントです。色彩豊かな「芭蕉の間」と、墨絵の「孔雀の間」では、金箔の使用方法に違いが見られるとされており、これを分析することで応挙の芸術的技法に対する新たな理解が得られることを目指しています。
3. 江戸時代と明治時代の金箔比較
さらに、江戸時代に使用された金箔と、その後の明治時代に修復時に加えられた金箔の違いを定量的なデータで比較する機会も訪れます。このような詳細な資料は、円山応挙の画業や技法の理解に貢献するでしょう。
今後の展望
分析結果は、学術的な資源として活用されるほか、今後の文化財保全にも寄与することが期待されています。リガクは、このプロジェクトを通じて科学技術を駆使し、文化遺産の保全や未来への継承に貢献する姿勢を貫いています。
リガクグループのご紹介
リガクグループは、X線分析を中心に最新の分析技術を提供する企業であり、国内外でさまざまな分野において確かな影響力を発揮しています。1951年に設立以来、90カ国以上でお客様と共に成長を続けており、産業や研究用の分野で幅広く対応しています。詳しい情報は、rigaku-holdings.comをご覧ください。


トピックス(その他)


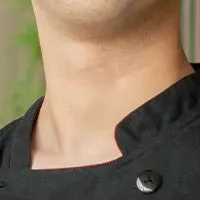


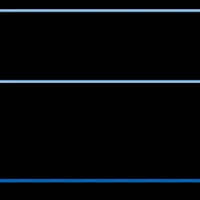

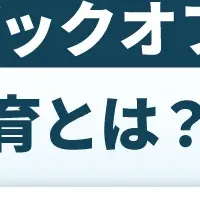


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。